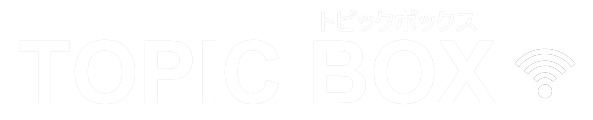「デジタルネイティブ」そのキラキラした肩書きを背負い、颯爽と社会に登場したZ世代。
スマホ片手に情報を操り、SNSを駆使して世界とつながる姿は、まさに未来からの救世主。
我々旧人類(ミレニアル世代以上)が必死で覚えた新しいアプリも、彼らにかかれば朝飯前です。
しかし、いざ戦場(オフィス)に降り立つと、彼らの前に立ちはだかる巨大な壁…それは「パソコン」という名の古代遺跡でした!
「え、Excelのセルの結合ってどうやるんですか…?なんか、セルが合体する魔法ですか?」
「PDFってなんですか?新しいスイーツ…?」
「電話は…ちょっと、心の準備が必要で…」
そんな新人たちのピュアすぎる瞳に、上司世代は頭を抱え、ネットの世界では「老害」の対義語として「若害(じゃくがい)」という禁断のパワーワードまで爆誕する始末。
一体なぜ、スマホの達人たちがパソコンの前でかくも無力になってしまうのでしょうか。
これは単なる世代間のギャップなのか、それとも日本社会が直面する新たな課題なのでしょうか。
今回は、ネットの世界に渦巻く悲喜こもごもの声を参考に、この奇妙で笑える(いや、もはや笑えない?)「Z世代のPCスキル問題」を面白おかしく、そしてちょっぴり真面目に深掘りしていきます!
オフィスに現れた新種族「PCフリーズ世代」の衝撃

「デジタルネイティブだから、ITスキルはバッチリだろう」
そんな淡い期待は、入社初日に木っ端微塵に砕け散ることも少なくないようです。
ネットの世界では、先輩社員たちの悲鳴にも似た目撃情報が後を絶ちません。
Case 1. Excelの迷宮に迷い込んだ勇者たち
オフィスソフトの王様、Excel。
我々にとっては当たり前のツールが、彼らにとっては難攻不落のダンジョンのようです。
「新人に簡単なデータ集計を頼んだら、『SUM関数ってなんですか?』と聞かれて、時が止まった」
「“セルの結合”という初級魔法で一日中苦戦していた。もはやラスボスとの死闘だったのかもしれない」
ネット上の声を聞いていると、まるでRPGの世界。
VLOOKUP関数なんて、伝説の魔法使いしか使えない禁断の呪文扱い。
ショートカットキーを使いこなす先輩は、まるで指先から魔法を放つ賢者のように見えるのだとか。
スマホアプリなら直感的に操作できるのに、なぜPCはこんなに複雑なんだ!という彼らの心の叫びが聞こえてきそうです。
画面を指でスワイプして「あれ、動かない…」と呟く姿は、もはや職場の風物詩となりつつあるのかもしれません。
Case 2. オンライン会議で消える新人
リモートワークが普及し、必須スキルとなったオンライン会議。
しかし、ここにもZ世代を苦しめる罠が潜んでいます。
「画面共有のボタンがどこにあるか分からず、会議の半分を“探しています…”で過ごした新人」
「マイクがミュートのまま熱弁を振るい、チャットで総ツッコミを受ける悲劇」
スマホならタップ一つで済む操作が、PCだと途端に複雑怪奇なシステムに見える…。
「テック・シェイム(デジタル機器をうまく使えない恥ずかしさ)」を感じ、人知れず心を痛めている若者もいるというから、一概に笑ってばかりもいられません。
なぜ?「スマホは達人、パソコンは素人」が生まれるワケ

この不可解な現象は、なぜ起きるのでしょうか。
その背景には、Z世代が育ってきた特有の環境が大きく影響しているようです。
理由1. スマホ万能帝国の誕生
彼らが物心ついた頃には、すでにスマートフォンが世界の中心でした。
調べ物、連絡、買い物、課題の提出、果ては卒業論文まで…すべてが手のひらの上で完結する「スマホ万能帝国」の国民なのです。
わざわざ起動に時間がかかる大きな箱(PC)に向かう必要がない。
その結果、キーボードのタイピングよりもフリック入力が爆速になり、マウス操作よりもスワイプ操作が体に染みついてしまったのです。
便利すぎるスマホが、皮肉にもPCスキルという翼を奪ってしまったのかもしれません。
理由2. 学校教育のデジタル化、その光と影
「いやいや、学校でパソコン習ったでしょ?」というツッコミが聞こえてきそうですが、ここにも落とし穴が。
近年、GIGAスクール構想で一人一台タブレットが配布される学校が増えました。
しかし、ネットの世界の声を見ると、「タブレットは配られたけど、キーボードやマウスに触れる機会は少なかった」「情報の授業はあったけど、実践的なOfficeソフトの使い方は…」といった意見も。
学校で使うのは、あくまで学習用のアプリやブラウザが中心。
企業で求められるような「データ集計」や「企画書作成」といったゴリゴリのビジネススキルとは、少し毛色が違うようです。
ネットで勃発!「若害 vs 老害」世代間大乱闘

この問題は、ネットの世界で世代間のバトルロイヤルを引き起こしています。
様々な立場の意見が飛び交い、カオスな状況に。
嘆きのベテラン勢「ワシらの若い頃は…」
「電話も出ない、PCも使えない。じゃあ一体何ができるんだ!」
「こっちはパワハラって言われないように、腫れ物に触るように接してるのに…」
「氷河期世代は、誰も教えてくれなくても必死で覚えたんだぞ!甘えるな!」
上の世代からは、戸惑いや憤りの声が噴出。
特に、就職難で苦労した氷河期世代から見れば、売り手市場で「すぐ辞める」「権利ばかり主張する」と映るZ世代の姿に、複雑な感情を抱くのも無理はないのかもしれません。
Z世代擁護派の正論パンチ「教えればいいじゃん」
「最初から完璧な新人なんていない。教えればすぐ覚えるでしょ」
「そもそも、おじさん世代だってスマホの新しい機能にはついていけてないじゃないか」
「世代で一括りにするな。できるZ世代はめちゃくちゃできる」
一方、冷静な意見も多数。
たしかに、若者の吸収力は凄まじいものがあります。
最初は戸惑っても、数ヶ月もすればベテラン顔負けのショートカットキー使いに変貌を遂げる可能性も秘めています。
そもそも、新しいことを覚える姿勢は、どの世代にも必要なはずです。
救世主はゲーマーだった!?「PC強者はだいたい友達」
そんな中、一つの光明が差し込みます。
それは「PCスキルが高い若者は、だいたいゲーマー」という説。
「うちの新人でPCにやたら詳しい子は、例外なくゲーミングPCを自作するレベルのゲーマーだった」
「オンラインゲームのチャットで鍛えられたタイピング速度は伊達じゃない」
グラフィックボードの性能を語り出し、ショートカットキーを駆使して作業効率を爆上げする若きゲーマーたち。
彼らは、スマホ帝国に生まれたレジスタンスなのかもしれません。
企業の人事担当者は、面接で「好きなゲームは?」と聞いてみるのが、意外な近道になる時代が来る…かも?
若害はPCスキルだけじゃない?Z世代の謎生態

この問題、実はPCスキルだけに留まりません。
ネットの世界では、Z世代の仕事に対する価値観そのものが議論の的になっています。
電話恐怖症シンドローム
「電話が鳴っても絶対に出ない。まるで時限爆弾でも見るかのような目で電話機を見つめている」
「『理系なので電話対応はしません』という謎理論を振りかざす新人がいる」
チャットやDMがコミュニケーションの基本である彼らにとって、相手の時間を強制的に奪う「電話」は、非常にハードルの高いツール。
顔の見えない相手と、準備なく話さなければいけない恐怖は、我々の想像以上なのかもしれません。
鋼の自己肯定感とガラスのハート
「仕事はできないのに、口だけは一丁前。SNSの受け売りで社会を語る」
「注意したら『パワハラだ』と騒ぐか、次の日から来なくなる」
自己肯定感を高く保つ教育を受けてきた一方で、打たれ弱さも指摘されるZ世代。
彼らにとって「注意」は「人格否定」と受け取られかねない危険な行為。
上司たちは、言葉の地雷原を慎重に歩くような、高度なコミュニケーションスキルを求められています。
若害を乗り越え、共に未来へ

さて、ここまで面白おかしくZ世代の「若害」問題を見てきましたが、ただ対立を煽っていても何も生まれません。
このギャップをどう乗り越えていけばいいのでしょうか。
企業に求められる「育成アップデート」
「デジタルネイティブ=即戦力」という幻想は捨て、新人研修に「Excel入門」「ビジネスメールの書き方」といった基礎講座を組み込む企業が増えています。
知らないことを「できない」と切り捨てるのではなく、教える環境を整える。
これは、いつの時代も変わらない企業の使命です。
上司世代の「翻訳スキル」
Z世代は「タイパ(タイムパフォーマンス)」を重視します。
ダラダラと精神論を語るより、「このショートカットキーを使えば、作業時間が半分になるよ」と具体的に教える方が響くかもしれません。
彼らの言語や価値観を理解し、「翻訳」して伝える努力が、心の壁を溶かす鍵となります。
Z世代よ、恐れるな!
初めてのPC操作、初めての電話対応。
誰だって最初は戸惑うものです。
スマホを使いこなすその柔軟な頭脳があれば、PCスキルなんてすぐに身につきます。
わからないことは恥ずかしいことではありません。
「ググる力」は君たちの得意分野のはず。
どんどん調べて、聞いて、試して、古代遺跡(PC)を乗りこなし、最強のデジタル戦士になってください!
【若害】警報発令!Z世代はPCの赤子?ポイントまとめ
「若害」という言葉は、世代間の価値観のズレが生んだ、ちょっぴり刺激的な流行語かもしれません。
しかし、その根底にあるのは、お互いの「当たり前」が違うことへの戸惑いです。
上の世代は「これくらいできて当たり前」と思い、Z世代は「スマホでできないなんて不便」と感じる。
この溝を埋めるのは、一方的な批判ではなく、歩み寄りの心です。
笑い合い、教え合い、時にはぶつかり合いながら、新しい時代の働き方を作っていく。
そうすれば、「若害」も「老害」も笑い話になる日が、きっと来るはずです。